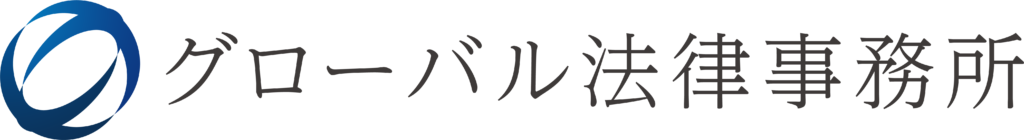下請法の改正(弁護士 村上智裕)
下請法(「下請代金支払遅延等防止法」)が2025年5月16日に改正されました。
改正下請法が目指すものは、「構造的な価格転嫁の実現」です。近年、労務費、原材料費、エネルギーコストなどが急激に上昇していますが、かようなコスト上昇について中小の受託事業者のみが負担を押し付けられるというのはおよそ健全な環境とはいえません。中小企業、物流事業者が厳しい環境に置かれている現状をうけ、サプライチェーン全体で適切に価格転嫁をさせることを目的として今回の改正が行われました。
改正法(改正に伴い、法律の名前も「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変わりました)は、2026年1月1日から施行されます。
改正法では、用語についても、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」等に改めています。
改正法において、規制の見直しがあったのは主に以下の点です。これまでの取扱いで問題ないか、見直しが必要ではないか、ご確認いただければと思います。
1 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
従来の下請法では、買いたたきや下請代金の減額など、対価を不当に引き下げる方向での行為(対価引き下げ型)を規制していました。
この点、改正法では、従来の規制とは別途、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、委託事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定して、中小受託事業者の利益を不当に害する行為を禁止する規定(交渉プロセスに着目した規定)を新設しました。
2 手形払等の禁止
従来の下請法では、一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付することを規制していましたが、改正法では、手形払いそのものを認めないこととしました。
また、電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては認めないことにしました。
3 規制対象となる取引への「運送委託」の追加
従来の下請法では、元請運送業者から下請運送事業者への委託(荷主から見ての「再委託」)については規制対象となっていましたが、荷主から元請運送事業者への運送委託は規制対象にはなっていませんでした。
この点、改正法では、運送業者が荷主により荷役作業や荷待ちを無償で強いられている情勢に鑑み、「物品の運送の再委託」に加えて、荷主から元請運送事業者への運送委託(「物品の運送の委託」)も規制対象に追加しました。
4 従業員基準の追加
従来の下請法では、親事業者と下請事業者の「資本金規模」と「取引の内容」によって対象となる取引を区分しておりましたが、改正法では、「従業員数」の基準を新たに追加しました。
改正法においては、(従来の適用対象に加えて)“製造委託等の取引においては従業員数300人”、“役務提供委託等の取引においては従業員数100人”を基準としており、それらの基準を超える法人事業者が、それらの基準以下の個人・法人と取引をする場合、前者は委託事象者(親事業者)、後者は中小受託事業者(下請事業者)として扱われることになります。
5 面的執行の強化
従来の下請法では、事業所管省庁には調査権限のみが与えられていましたが、改正法では、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限も付与しました。
また、この主務大臣の権限強化にあわせて、従来の下請法では、報復措置の禁止(親事業者が下請事業者の不公正な行為を公正取引委員会等に知らせたことを理由に、その下請事業者に対して不利益な取り扱いをすることを禁じるもの)の申告先が公正取引委員会及び中小企業庁長官に限られていたことについて、改正法では、事業所管省庁の主務大臣も追加しています。
6 その他
その他にも以下のような改正がなされています。
・製造委託の対象物品として、「金型」と同様に、専ら製品の作成のために用いられる「木型、治具等」を追加しました。
・書面等の交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を電磁的方法により提供可能としました。
・遅延利息の対象に減額を追加し、代金の額を減じた場合、起算日から60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、遅延利息を支払わなければならないものとしました。
・既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備し、勧告時点において委託事業者の行為が是正されていた場合においても、再発防止策などを勧告できるようにしました。
以上